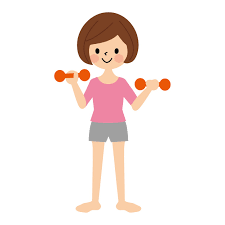小児アレルギーの連絡書等の提出書類の記載をご希望の方へ
~食物アレルギー・アナフィラキシー・乳糖不耐症連絡書/気管支喘息連絡書(総社市)
・学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(他市)の記載を希望される患者さまへ~
毎年、年初めから3月にかけて、アレルギーの書類の記載を希望され、多くの患者さまが来院されます。しかし、中には採血検査や試して食べてみることが必要で、すぐに書類を書けない場合があります。提出には期限がありますので、早めのご来院をお願いいたします。
又、余裕をもって診察や検査をするために、できる限り予約のアトピー外来の時間での受診をお願いいたします。
小児科の受診の際は親子手帳をお持ちください
小児科の受診の際は、医師が確認できるように、親子手帳(母子手帳)をお持ちください。
適切な診断につながりますので、必ずお持ちくださいますようお願いします。
小児科発熱患者様の診察、検査について
当院では、発熱以外の一般の患者様と、新型コロナウイルスを含む発熱患者様は時間で分けず、場所を分けて診察、検査しています。来院された際、車内に待機していただき電話で状態を伺い、診察を院内の隔離室で行うか、車内で行うかを決めています。隔離室には発熱以外の患者さんと交わらないよう隔離用入り口から入っていただき、室内滞在も短時間になるように努めています。
小児科・アレルギ-科について
アレルギー科
食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、じんましん、湿疹、小児の気管支喘息、アレルギー性鼻炎、花粉症などの診療が中心です。大人の気管支喘息の診療や金属アレルギーや光線過敏症の検査などはやっておりません。
基本的な考え
かゆみや鼻水などのアレルギーの症状を軽くする治療(対症療法)は大切ですが、原因対策もそれにもまして大切です。冷え症や胃腸の弱さなど体質の問題がある場合、漢方が役立つ場合がよくあります。おかれた環境の中で、食事や、睡眠、運動、ストレスへの対処・発散法など日々の生活をもう一度見直していただけるとしめたものです。例えば、寝るのが夜中の12時以降になると自律神経機能が落ちて、アレルギーを悪化させやすくなります。
食事では、基本的には、パンに牛乳、肉の洋食よりは、ごはんに味噌汁に野菜に豆や魚の和食をお勧めしています。皮膚や粘膜の問題には、経皮毒の洗剤にも目を向けて石けん化をお勧めしています。栄養士が常勤で務めていますので、食べることに関しては、いつでも栄養士に相談していただけます。どうぞお気軽にご利用ください。 
漢方のこと
乳幼児検診・ワクチン

・通常のワクチンは全ておこなっています。長く小児科をやっているとワクチンでどれだけ多くの命が救われ、こどもたちが安全に過ごせるようになったかを心の底から実感します。これからの医療は病気の予防に重点があります。必要なワクチンの接種は是非進めていきたいと考えます。
・乳幼児検診は6~7ヵ月、9~10か月、1才、2才児が主な対象ですが、3~4ヵ月や1歳半,3才児なども行っています。
発育・発達、疾患のチェックは最低限、基本に行うものですが、それ以外のささいな疑問や困られている事、できれば愚痴まで聞ける関係になれ、その子の成長を末長く見守ってゆけたらいいなと思います。
矢追インパクト療法
~当院独自の工夫でアレンジしています~
故矢追 博美先生が生み出された一種の免疫療法。花粉症、アレルギー性鼻炎の方を中心に、じんましんや湿疹や元気不足の方にも行っています。
代表的なアレルゲンの精製エキスを薄く希釈して一定の間隔でごく微量、皮内に注射します。苦手な刺激を適度な間隔で体に与えて、免疫を強くするイメージです。
 現在はハウスダスト、カンジダ、スギ花粉、カモガヤ花粉を用い、カンジダなら治療用エキスの一京倍(一兆の千倍)の溶液を使います。濃度がとても薄いので、注射でショックを起こす心配のない安全な治療法です。
現在はハウスダスト、カンジダ、スギ花粉、カモガヤ花粉を用い、カンジダなら治療用エキスの一京倍(一兆の千倍)の溶液を使います。濃度がとても薄いので、注射でショックを起こす心配のない安全な治療法です。原法の前腕ではなく前頭部の頭皮に注射するとあまり痛くないので最近よく用いています。 杉花粉の時期だけ治療に来られる方も多いですが、前任の病院時代に小学生から始められ2ヵ月に1回、24年間続けられている方がいます。お元気な最長記録者です!
矢追先生の著作本や遺稿集の貸し出しができます。どうぞお声かけください。
舌下免疫療法
花粉の飛ぶ季節になると、「くしゃみ連発、鼻汁だらだら、目もかゆくて」といった患者さんが多くなります。鼻水やくしゃみくらい、と思うなかれ。なってみるとしんどいものですね。単に症状を抑える内服や目薬や点鼻薬の治療とは違って、免疫を高めるアレルギー治療法として、当院では矢追インパクト療法を開院以来行ってきました。効果は明瞭でお勧めなのですが、注射がこわいお子さんや定期的に注射に通えない方には使えませんでした。
 そこで、この度、免疫を高める治療法の一つとして舌下免疫療法を開始しました。この治療は舌下から吸収させ、体の中に薄めた原因となるアレルゲンを入れ、抗体を作ることで症状を改善させる治療です。口の中(舌の下)にすぐに溶ける薄くて丸い錠剤をおくだけで、5才くらいのお子さんでも治療できます。初めの1週間のみ抗原量の少ない舌下錠を使い、その後は同じ抗原量の舌下錠の内服を毎日続けます。治療を開始すると、喉がイガイガ、鼻水が出る、口内炎ができるといった副作用が出る場合がありますが、大半の患者さんは2週間から1ヵ月程度で徐々に副作用の症状が消えていきます。初回のみアレルギー症状が出ないか30分院内で経過をみます。
そこで、この度、免疫を高める治療法の一つとして舌下免疫療法を開始しました。この治療は舌下から吸収させ、体の中に薄めた原因となるアレルゲンを入れ、抗体を作ることで症状を改善させる治療です。口の中(舌の下)にすぐに溶ける薄くて丸い錠剤をおくだけで、5才くらいのお子さんでも治療できます。初めの1週間のみ抗原量の少ない舌下錠を使い、その後は同じ抗原量の舌下錠の内服を毎日続けます。治療を開始すると、喉がイガイガ、鼻水が出る、口内炎ができるといった副作用が出る場合がありますが、大半の患者さんは2週間から1ヵ月程度で徐々に副作用の症状が消えていきます。初回のみアレルギー症状が出ないか30分院内で経過をみます。
通院間隔は初めは1~2週間後ですが、そのあとは何も問題なければ1か月に1回でも大丈夫です。治療の開始時期は、スギは花粉の飛散時期をさけるため6月~12月からになります。ダニの舌下免疫療法はいつからでも開始できます。対症療法ではないので、即効性はありませんが、数シーズンも待たずに効果が実感できる方が多いようです。
症状にお困りで関心のある方は、小児科・アレルギー科上田(か看護師)にお気軽にお声かけください。
肥満・肥満症